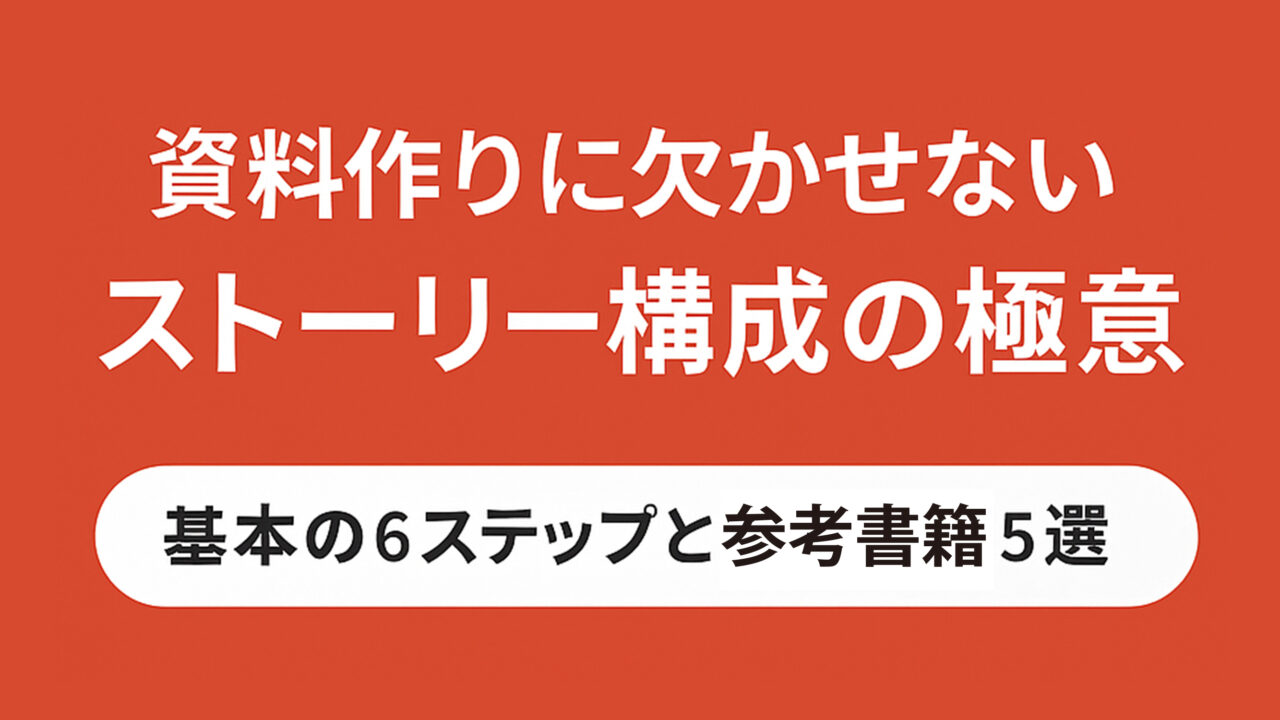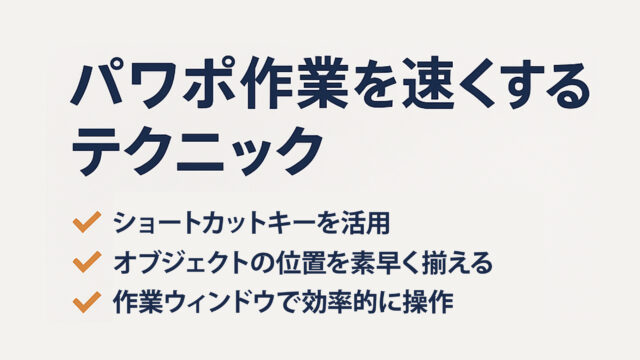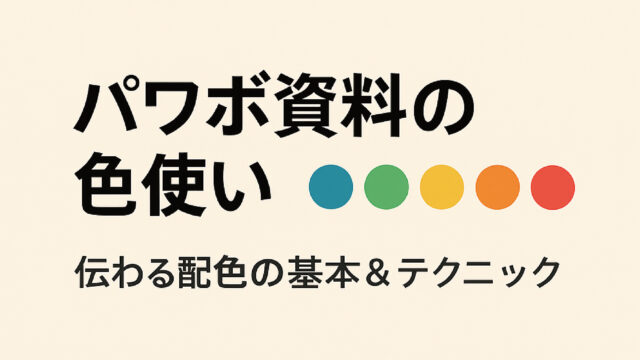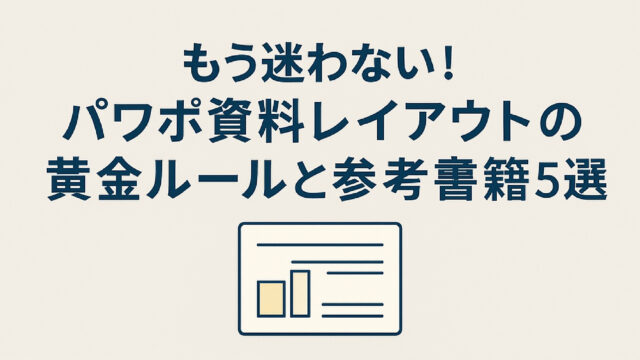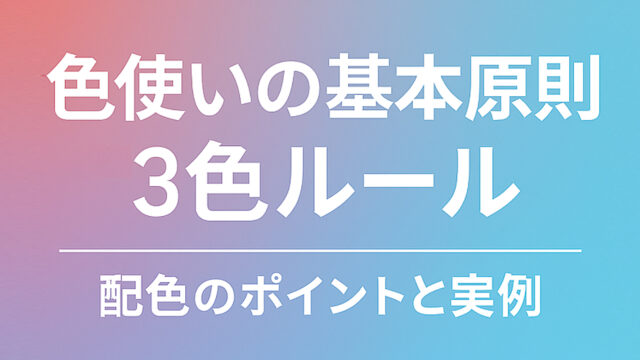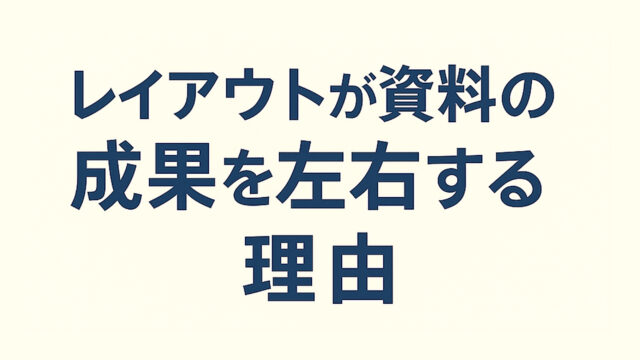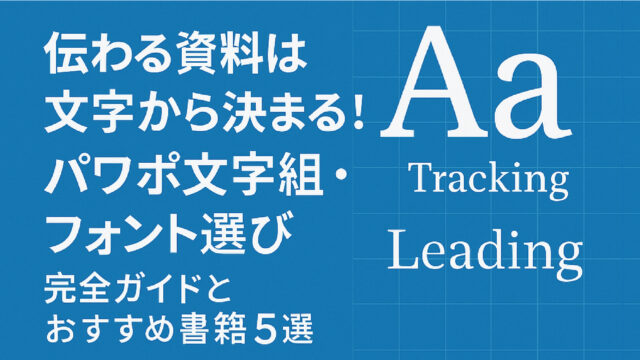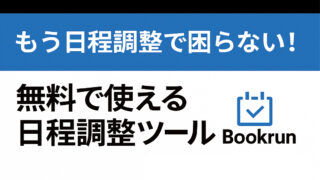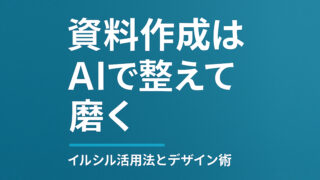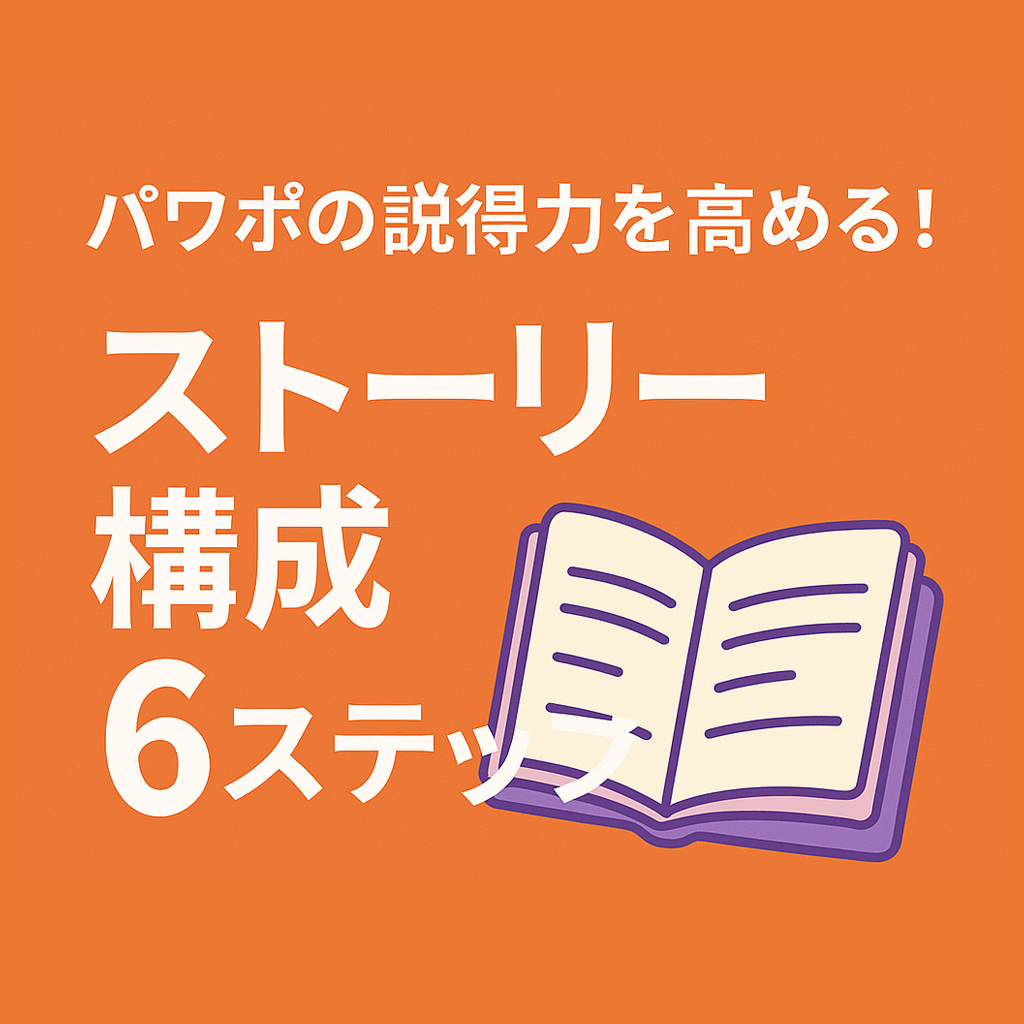
はじめに
なぜ資料にストーリー構成が必要なのか
あなたはパワポ資料を作るとき、どんな順番でページを並べていますか?
多くの人は「伝えたい情報を思いついた順」に並べがちですが、それでは聞き手の心に残りません。
プレゼンや会議資料に求められるのは情報を並べることではなく、納得させることです。
そのためには、ストーリー性のある構成が欠かせません。
ストーリー構成を取り入れると、
- 聞き手が自然に理解しやすくなる
- 記憶に残りやすくなる
- 行動を促しやすくなる
という効果が期待できます。
次から紹介する「5ステップ」で、あなたの資料作りを一段レベルアップさせましょう。
ステップ①:目的とゴールを明確にする
まずは「この資料で何を達成したいのか」を一文で言語化しましょう。
目的がブレた資料は、どんなにデザインが良くても伝わりません。
例:
- NG:「製品について説明する」
- OK:「製品の特徴と導入メリットを理解し、来月の契約意向を高めてもらう」
この一文を決めることで、構成やページ内容の判断基準ができます。
もし迷ったら、「この資料を見た後、相手にどんな行動を取ってほしいか」から逆算してください。
ステップ②:聞き手の立場を理解する
同じテーマでも、聞き手によって資料の切り口は大きく変わります。
経営層、現場担当者、顧客… それぞれに響くポイントは異なります。
ポイント:
- 知識レベル(専門用語は理解できるか?)
- 関心の軸(コスト削減?効率化?ブランド価値?)
- 立場による期待(意思決定者か、実務担当か)
ペルソナ(典型的なターゲット像)を一人設定し、その人に語りかけるつもりで構成を作ると効果的です。
ステップ③:ストーリーの流れを設計する
資料作成において「流れ」は骨格そのものです。
骨格がしっかりしていれば、デザインや装飾はあとから足しても崩れません。
逆に、流れが弱いと見栄えは良くても説得力がない資料になります。
「始まり・中盤・終わり」の3幕構成をベースにする
映画や小説と同じく、資料も導入・展開・結論の3幕構成にすると分かりやすくなります。
- 導入(始まり)
「なぜこの話を聞く必要があるのか」を示すパート。
聞き手の関心を引くフック(課題、データ、共感できる事例)を置きます。- 例:「市場は年率◯%で成長しているが、御社はシェアが横ばいです」
- 心理的には「このままではまずい」という課題感を醸成
- 展開(中盤)
課題の深掘り→原因→解決策という流れ。
聞き手が「確かにその解決策が必要だ」と納得する道筋を設計します。- 例:
- 課題の裏付けデータ
- なぜそれが起きているのか(原因分析)
- 解決策の全体像(ロードマップ)
- 例:
- 結論(終わり)
解決策の具体的効果や、次のアクションを提示します。- 例:「3か月以内に◯◯を導入し、半年後にKPI達成を目指しましょう」
- 心理的には「やってみよう」と思わせる動機づけ
流れを作る3つの型
資料の目的や相手によって、流れの型を選びます。
- A. PREP法(Point→Reason→Example→Point)
- 結論から始めたい場合(経営層向け、短時間プレゼン)
- 例:
- 「新規ツール導入で作業時間が40%削減できます」
- 「理由は、現在の工程の50%が手作業だからです」
- 「具体的に、A社では導入後に○○の成果がありました」
- 「だから、このツールを導入すべきです」
- B. 問題解決型(Problem→Cause→Solution→Benefit)
- 提案や営業資料に最適
- 例:
- 「現状、御社のサイトは離脱率が高い」
- 「その原因はページ速度の遅さと情報の分散です」
- 「改善策はサイトのUI再設計と高速化」
- 「これによりCV率が◯%向上します」
- C. ストーリーテリング型(主人公・課題・解決)
- 感情を動かしたい場合に有効(採用説明、ブランドストーリー)
- 例:
- 主人公(顧客や社員)の現状描写
- 直面する課題や苦労
- 解決方法と成長の様子
ページ間の「つなぎ」を意識する
流れが良くても、ページ間の接続が悪いと急に話が飛んだ印象になります。
各ページの最後に次ページへの予告要素を入れると、自然に読み進められます。
例:
- 「では、なぜこのような状況になっているのでしょうか?」
- 「次に、具体的な解決策をご紹介します」
起伏をつけて緩急をつける
同じテンションの情報が続くと、聞き手は飽きます。
- 数字や事実 → グラフやビジュアル
- 理論 → 事例
- 文字多めページ → 写真や図だけのページ
といった具合に、資料内のリズムを作りましょう。
最後に「行動喚起」で締める
結論ページでは必ず「この後どうしてほしいか」を明記します。
- 「◯月までに導入可否を判断」
- 「次回の打ち合わせで見積もりを提示」
- 「テスト運用に同意してほしい」
これを入れないと、せっかくの流れが「で、どうするの?」で終わってしまいます。
ステップ④:章立てとページ配分を決める
章立ては「導入 → 本論 → 結論」という大枠で作りましょう。
ページ配分のコツは重要な章に厚みを持たせること。
例:全20ページの場合
- 導入:3ページ
- 本論:12ページ
- 結論:5ページ
情報量が多い章では、見出しページや要約ページを挟むと流れが途切れにくくなります。
ステップ⑤:視覚要素を流れに合わせて配置する
文字だけの資料はどうしても飽きられます。
ストーリーの節目に、図・グラフ・写真を入れてテンポを作りましょう。
ポイント:
- グラフや図は1ページに1つまで(詰め込みすぎない)
- 同じ情報は文字と図の両方で見せると理解度が高まる
- 「見せ場ページ」は文字を減らし、ビジュアルで印象づける
ストーリー構成を磨くおすすめ書籍5選
1. 『イシューからはじめよ ― 知的生産の「シンプルな本質」』安宅和人
- ポイント:資料作成において「何を伝えるべきか」という本質的なテーマ設定力を磨ける。
- 学べること:
- 無駄な情報をそぎ落とし、重要な論点(イシュー)を見極める方法。
- 資料を作る前の段階で「これを話す意味はあるのか?」を明確化。
- 資料作りへの応用:
- プレゼンの導入や結論部分で軸がブレなくなる。
- ストーリー全体の骨組みを強化できる。
- → Amazonで見る
2. 『ストーリーとしての競争戦略 ― 優れた戦略の条件』楠木建
- ポイント:ビジネス戦略を「物語」として設計する手法を学べる。
- 学べること:
- 戦略をストーリーとして組み立てるメリットと具体例。
- 伏線、因果関係、感情の動かし方。
- 資料作りへの応用:
- 提案資料や企画書で、ロジックと感情を両立させるストーリー設計ができる。
- 数字だけではなく「語れる資料」に変わる。
- → Amazonで見る
3. 『伝えることから始めよう』伊藤羊一
- ポイント:シンプルかつ響くプレゼン構成の実践書。
- 学べること:
- 聞き手の心をつかむ「話の最初の15秒」の作り方。
- 情報の順序と盛り上げ方の基本。
- 資料作りへの応用:
- 導入部分や重要スライドの見せ場を作るのに役立つ。
- 会議・プレゼンのストーリー展開を短時間で組み立てられる。
- → Amazonで見る
4. 『シナリオの基礎技術』新井一
- ポイント:映画や小説の構成技術をビジネス資料に応用できる。
- 学べること:
- 三幕構成、起承転結、伏線回収といった物語の型。
- キャラクターや背景の設定がストーリーを支える重要性。
- 資料作りへの応用:
- 商品説明や事例紹介を物語化し、記憶に残る資料を作れる。
- 長時間のプレゼンでも飽きさせない流れ作り。
- → Amazonで見る
5. 『スティーブ・ジョブズ 驚異のプレゼン』カーマイン・ガロ
- ポイント:Appleのプレゼンを分解し、魅せる構成術を解説。
- 学べること:
- メッセージの絞り込み方、リズムある構成、視覚要素の使い方。
- 感情に訴えるためのストーリー演出テクニック。
- 資料作りへの応用:
- 製品紹介やコンセプト説明において、説得力と感動を両立。
- 見せ場のスライド構成が磨かれる。
- → Amazonで見る
まとめ
パワポ資料の完成度は、デザインよりもまずストーリー構成で決まります。
- 目的とゴールを明確化
- 聞き手の立場を理解
- 流れのパターンを選択
- 章立てとページ配分を設計
- 視覚要素でテンポをつける
この5ステップを押さえることで、説得力のある資料が作れるはずです。
次の資料作りでは、ぜひ今回の方法を取り入れてみてください。
そして、より深く学びたい方は今回紹介した書籍を活用すれば、ストーリー構成スキルが格段に上がります。