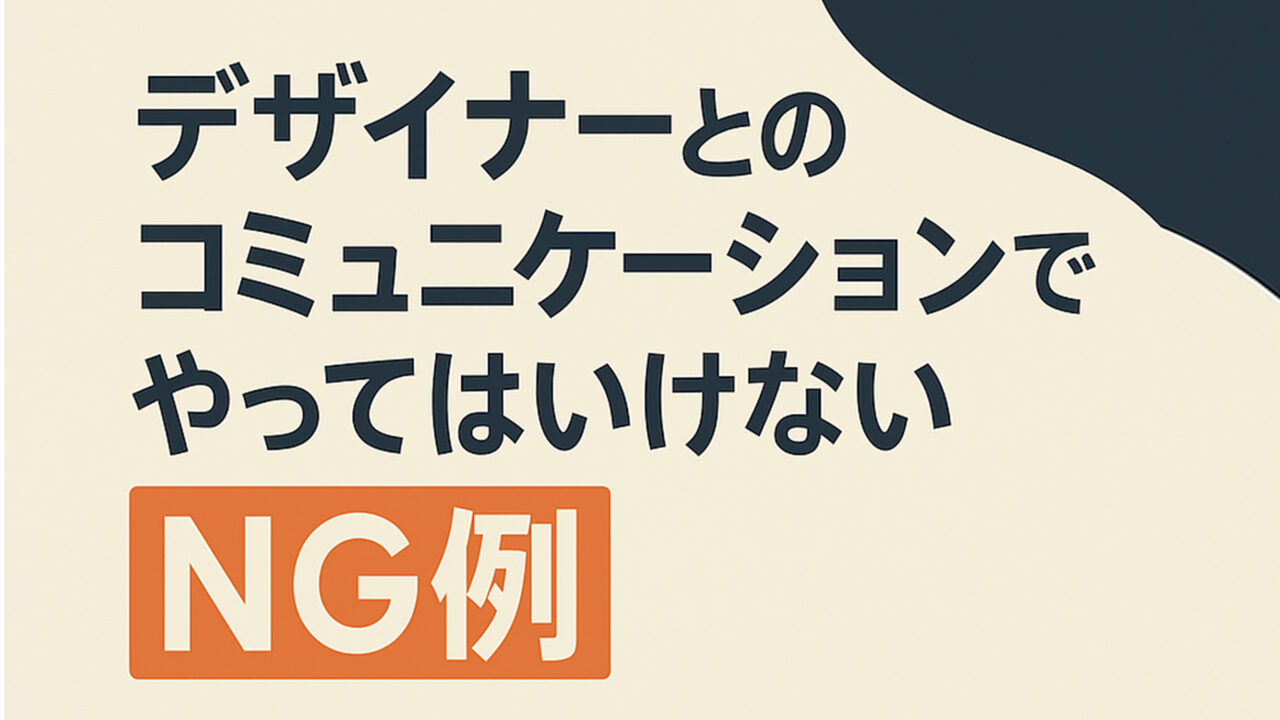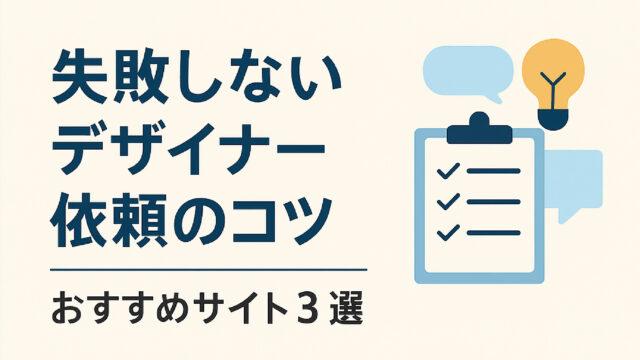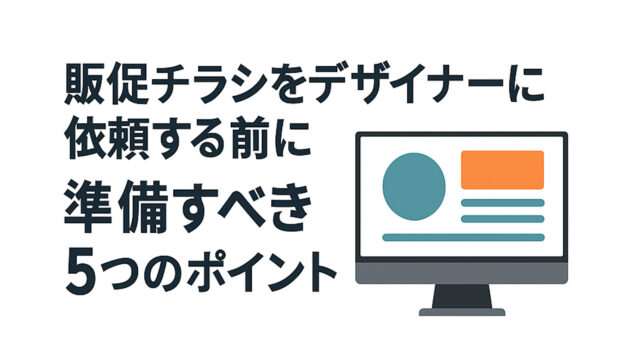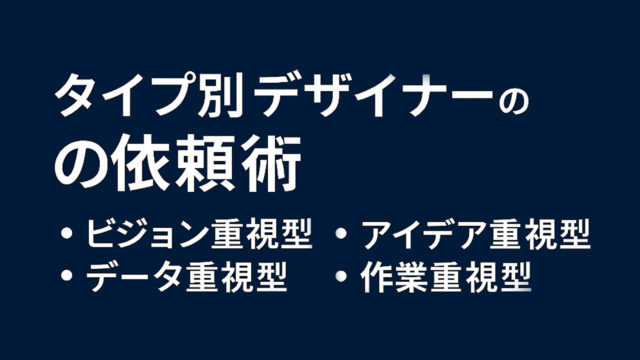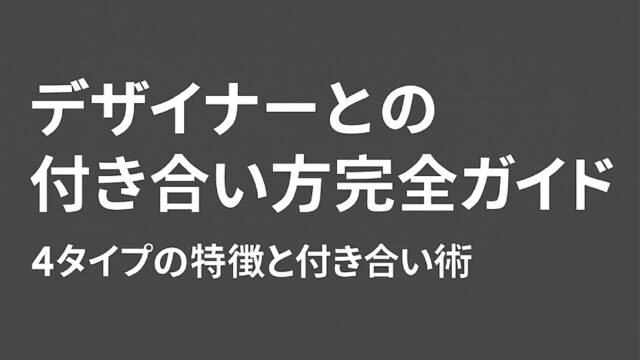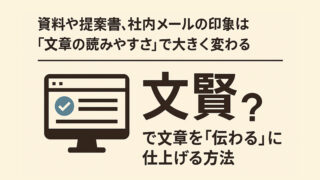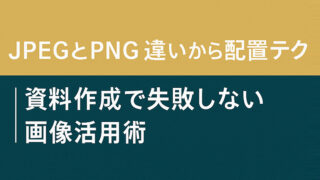はじめに
「いい感じでお願いします」
この一言、デザインのやり取りで使ったことはありませんか?
依頼する側は軽い気持ちでも、デザイナーにとっては危険なサインです。
なぜなら「いい感じ」の基準は人によって異なり、依頼者とデザイナーの頭の中の完成イメージが一致しないまま制作が進んでしまうからです。
デザイン制作は依頼者とデザイナーが協力してゴールを作る共同作業です。
そして、この共同作業の成否は、デザインスキルだけでなくコミュニケーションの質に左右されます。
本記事では、よくあるNG例とその改善策を、現場で役立つ具体事例とともに紹介します。
やり取りでよくあるNGパターン
抽象的な依頼
例:「もっとオシャレに」「いい感じで」
抽象的な言葉は、依頼者のイメージを正確に伝えられません。
結果としてデザイナーは自分の解釈で作業を進めるため、仕上がりが大きくズレるリスクがあります。
事例
Webバナー制作で「もっと明るく」とだけ指示したら、想定よりもカジュアルでポップな配色になってしまい、再制作に。
否定だけのフィードバック
例:「なんか違う」「もっとよくして」
この言葉だけでは、何がどう違うのかが不明確です。
デザイナーは改善方向を探るために複数案を試す必要があり、修正回数が増えます。
事例
社内資料の表紙デザインに対して「違う」とだけ伝えた結果、修正版が方向性の異なるものになり、再調整に時間がかかった。
優先順位を伝えない修正依頼
軽微な修正と重要な修正を同じ優先度で依頼すると、作業順序を誤り、納期までに重要部分が完成しない可能性があります。
事例
プレゼン資料の修正依頼で、細かい装飾変更と重要なグラフ差し替えを同列に依頼。軽微な修正に時間をかけすぎ、肝心なグラフ修正が納期ギリギリに。
突然の仕様変更
制作が進んでからの大幅な変更は、スケジュールやコストに直結します。
事例
印刷物の入稿前日に「縦型から横型に変えたい」と依頼。レイアウト再設計が必要になり、納期延長と追加費用が発生。
感情的な言葉
例:「全然よくない」「センスない」
こうした言葉は改善の方向性を示さないだけでなく、関係性を悪化させます。
事例
外注ポスター制作で感情的な否定をした結果、デザイナーとの信頼が崩れ、以降の提案も消極的になった。
NGを防ぐための正しい伝え方
具体的な基準を示す
NG:「もっとオシャレに」
OK:「この参考画像の配色に近づけたい」「フォントはゴシック体で」
具体的な色コードや書体名を示すことで、ズレを防げます。
改善方向を添える
NG:「なんか違う」
OK:「色はこの系統に、文字サイズは10%大きく」
改善案を添えれば、修正が的確に進みます。
優先度を明確にする
「必須修正」と「できれば修正」に分類して伝えることで、限られた時間でも最重要箇所が完成します。
変更理由を共有する
デザイナーが背景を理解すると、より適切な提案が可能になります。
事例:「今回の配布先は学生が多い」と伝えたところ、フォントや色味がターゲットに合うよう改善された。
敬意と感謝を言葉にする
「この部分は特に良い」「迅速な対応ありがとうございます」と添えることで、モチベーションと信頼が向上します。
実務で使える依頼・修正依頼のチェックリスト
□ 目的を明確に書いたか
□ 変更箇所を特定できているか
□ 変更理由を共有しているか
□ 優先度を設定しているか
□ スクショやPDFへの書き込みを添付したか
□ 言葉だけでなく視覚情報を補足したか
□ 依頼文に敬意と感謝を含めたか
このチェックリストをプロジェクト開始時から徹底すれば、修正回数・納期遅延・認識ズレが大幅に減ります。
コミュニケーション改善で得られる効果
修正回数の削減
指示が具体的であればあるほど、デザイナーは迷いなく作業に着手できます。
「なんとなく」の依頼では、依頼者の意図と異なる方向へ進みやすく、その都度修正が必要になります。
逆に、色コードやフォント名、参考画像などの具体情報を添えれば、初稿の完成度が格段に上がります。
結果として、修正回数が1〜2回で済み、全体の作業時間が短縮されます。
納期短縮
修正回数が減れば、当然スケジュールにも余裕が生まれます。
また、優先順位を明確に伝えておけば、限られた時間でも重要な部分から着手でき、納期遅延のリスクが下がります。
たとえば、印刷物の制作では、入稿日が固定されているため、デザイン修正に充てられる時間は限られます。
このとき「必須修正=表紙デザインの差し替え」「希望修正=ページ番号のデザイン変更」と切り分けることで、重要部分だけでも確実に完成できます。
信頼関係向上
デザイン業務は依頼者とデザイナーの信頼関係が成果に直結します。
依頼が的確で、背景や意図まで共有されていれば、デザイナーは「この人はプロジェクト全体を理解してくれている」と感じ、安心して提案や改善案を出せます。
また、依頼や修正時に感謝や評価の言葉を添えることで、モチベーションが上がり、より良い提案を自主的に行ってくれる関係性が築けます。
品質安定
指示の精度が高まると、制作物のクオリティにバラつきがなくなります。
特に継続案件では、毎回の成果物に一貫性が生まれ、ブランドイメージが安定します。
例えば、社内プレゼン資料や販促物では、色・フォント・レイアウトが揃うことで、受け手に与える印象が「統一されたプロフェッショナル」に変わります。
これは単なる見た目の問題ではなく、組織全体の信頼感にも影響します。
まとめ
- 修正回数削減は工数削減とコスト低減につながる
- 納期短縮は突発的な変更や追加依頼にも対応できる余裕を生む
- 信頼関係向上は提案の質を上げ、長期的な協力関係を築く土台になる
- 品質安定はブランドや組織の印象を強化する
おすすめ書籍
1. ビジネス文章・資料作成
- 『新しい文章力の教室』唐木元 著
文章構成や推敲のコツをわかりやすく解説。資料文の質向上にも直結。
- 『伝わるデザインの基本』高橋佑磨 著
資料やチラシのデザイン原則を初心者にもわかりやすく解説。
2. デザイン依頼・外注コミュニケーション
- 『センスは知識からはじまる』水野学 著
デザインの判断基準を持つための必読書。依頼者側の感覚を養える。
3. プレゼン・パワポ資料術
- 『一生使える見やすい資料のデザイン入門 完全版』
スライドの構成や見せ方の基本が学べる。
- 『 見せれば即決! 資料作成術』天野暢子 著
相手の行動を引き出す資料作りの思考法。
4. コミュニケーション術
- 『人を動かす』D・カーネギー 著 相手との関係を良好に保つ会話術の古典。
- 『フィードバック入門』篠原信 著 改善点を効果的に伝える方法が身につく。
まとめ
デザイナーとのやり取りで起こる多くの問題は、「意図が共有されていない」ことが原因です。
抽象的な依頼や否定だけのフィードバックは、方向性のズレや修正の迷走を招きます。
改善のポイントは3つ。
- 具体性を持たせる
- 背景を共有する
- 優先度を明確にする
デザイン依頼は発注ではなく共同制作です。
適切なコミュニケーションを積み重ねれば、成果物の質も、関係性の質も確実に向上します。