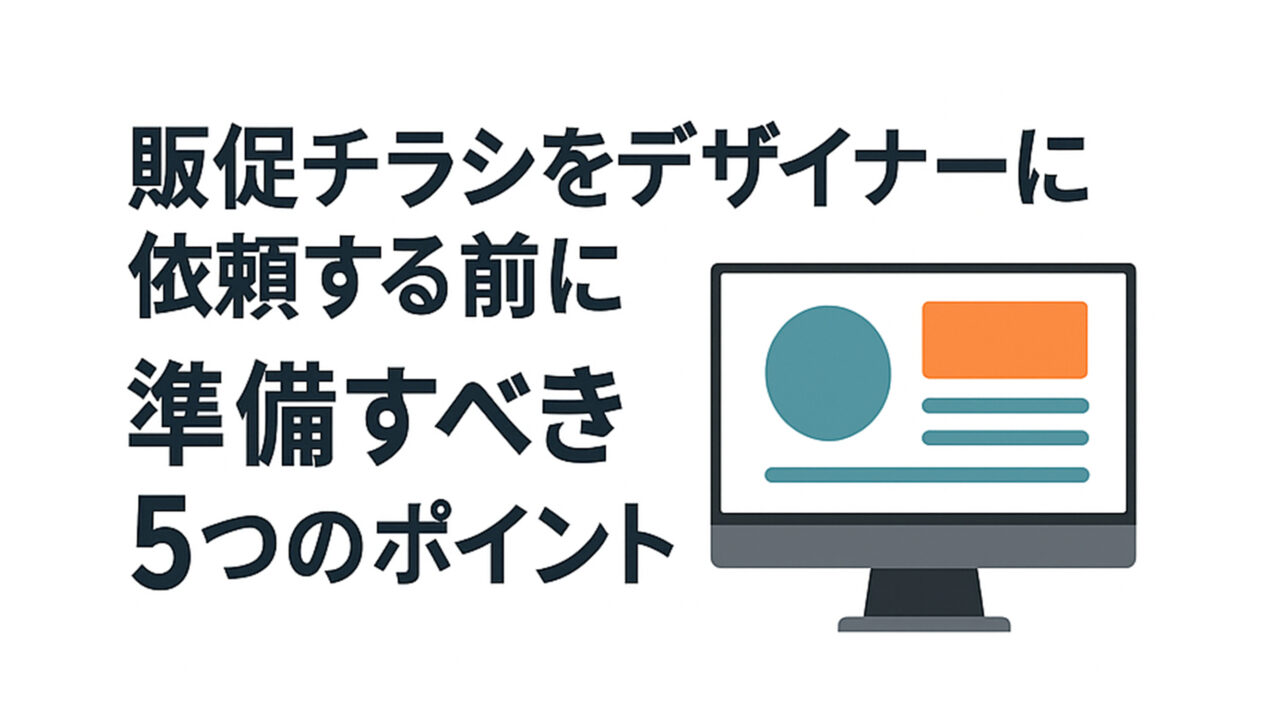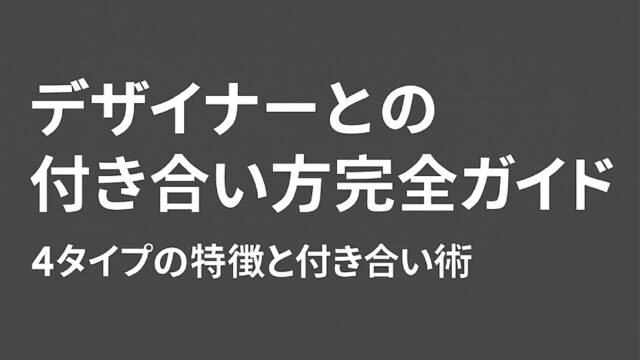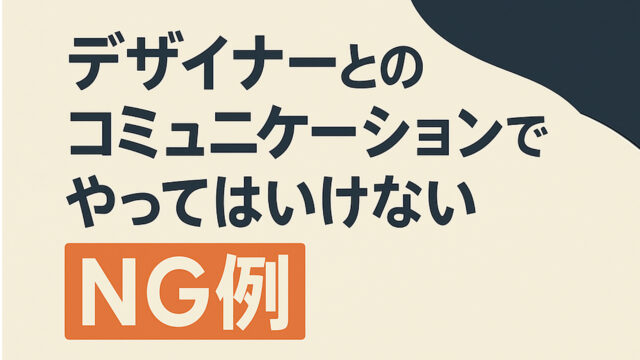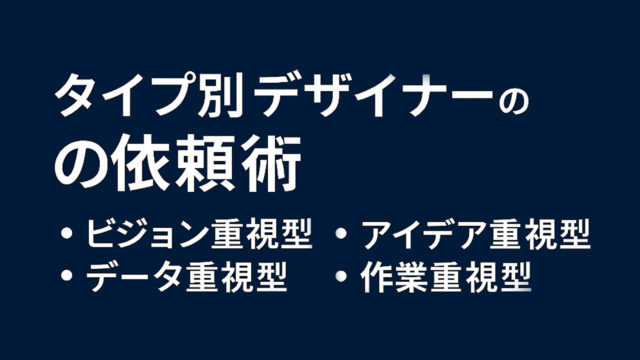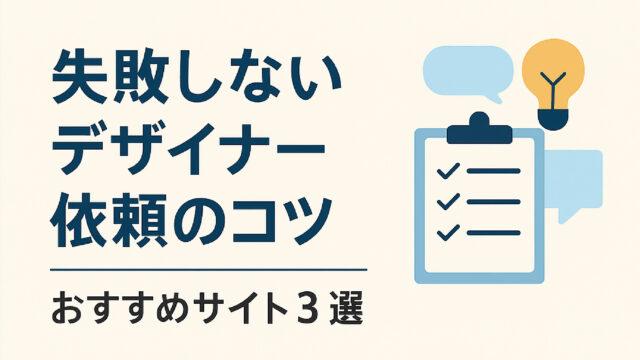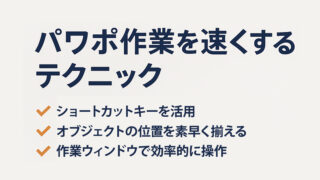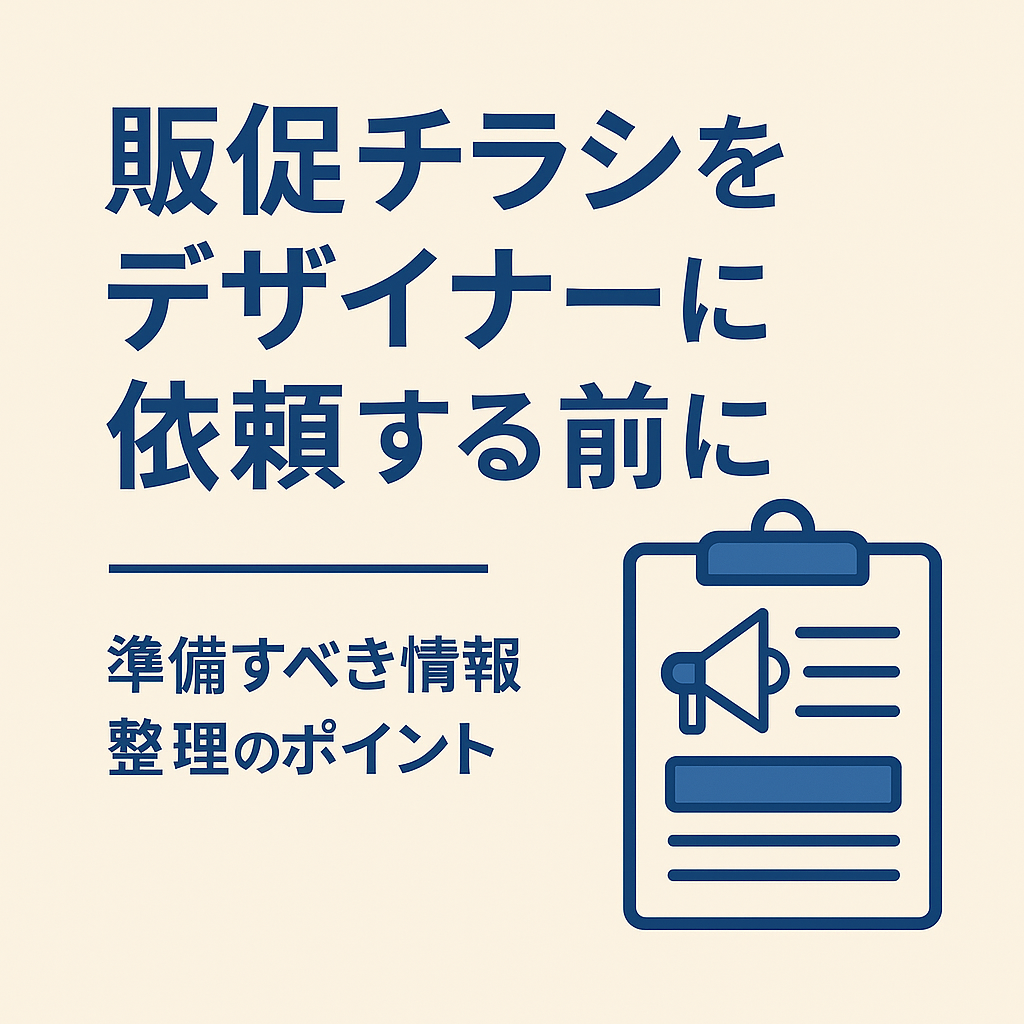
はじめに
なぜ「依頼前の準備」が成果を左右するのか
販促チラシは、店舗やサービスを知ってもらうための「最初の接点」になりやすいツールです。
ただし、その重要性とは裏腹に、「デザインはプロに任せれば大丈夫」と考えて、準備をほとんどせずに依頼してしまうケースも少なくありません。
結果どうなるか?
- 情報が散らかって「結局何を伝えたいのか分からないチラシ」になる
- 修正依頼が何度も発生して納期が遅れる
- デザイン費用が膨らむわりに効果は出ない
こうした失敗の多くは、依頼前に依頼者が考えておくべきことを整理していないことが原因です。
「丸投げ依頼」の落とし穴
「売上を上げたい」「もっと知名度を広げたい」といった抽象的なゴールだけでは、デザイナーは判断の材料を持てません。
結果として「なんとなく目立つデザイン」は作れても、「成果に直結するデザイン」にはなりません。
たとえば…
- ✗ 「売上を上げたい」→ デザインの方向性が定まらず、配色・コピー・構図がバラバラになる
- ◯ 「新規オープンのカフェに、20代女性客を呼び込みたい」→ ターゲットが明確なので、写真選びやフォント、チラシのサイズ感まで一貫した方向性で進められる
完璧に固める必要はない
ここで誤解しやすいのは「すべてを決めてから依頼しないといけない」という考え方です。
実際はそこまで厳密でなくても大丈夫です。
必要なのは、最低限の“軸”を言語化しておくこと。
「目的」「ターゲット」「配布シーン」などが共有されていれば、デザイナーはその軸をもとに最適な提案を行えます。
依頼前準備=共通言語づくり
依頼者とデザイナーは、立場も専門性も異なります。
依頼前の準備とは、両者の間に“共通言語”をつくる作業でもあります。
依頼者の頭の中にある「こうしたい」を言語化・可視化することで、デザイナーは「こう表現しよう」と的確に判断できるのです。
依頼前に必ず整理すべき5つのポイント
目的の明確化
目的が曖昧だと、チラシは「情報の寄せ集め」になってしまいます。
- ゴールを一文で書き出す
- 「認知拡大」「来店促進」「イベント参加」など行動を定義する
失敗例
「とにかく全部伝えたい」→情報過多で、読者は結局何も覚えない
改善例
「4月のオープン記念キャンペーンに来店してほしい」→見出しやビジュアルも“来店”を中心に構成できる
ターゲット設定
「誰に見てもらうのか」が明確でないと、メッセージもぼやけます。
- 年齢・性別・生活スタイル(20代女性/子育て中の主婦/経営者層など)
- 読者の「悩み」「行動動機」を想定
失敗例
「老若男女すべて」→結局フォントもトーンも中途半端になり、刺さらない
改善例
「週末のランチでおしゃれに過ごしたい20代女性」→写真もフォントも柔らかく、配色も明るい系で統一
配布シーンの想定
チラシの“出番”がどこなのかで、デザイン要件は大きく変わります。
- 駅前で配布 → 一瞬で目を引く必要。キャッチコピーは大きく。
- DM封入 → 落ち着いたデザインで、じっくり読ませる構成。
- 店頭設置 → 通りすがりでも手に取りやすいサイズ感と色味。
失敗例
駅前配布用なのに、文字が小さすぎて通行人が読めない
改善例
一番大きな見出しに「半額キャンペーン」と配置し、遠くからでも分かる
必須要素の整理
チラシには「必ず載せなければならない情報」があります。
- 店舗名・住所・電話番号・QRコード
- 開催日やキャンペーン期間
- 特典や値引き条件
失敗例
チラシが完成してから「住所を載せ忘れた!」と気づく
改善例
依頼前に「必須要素リスト」を作り、抜け漏れをゼロにする
トーン&イメージ
デザインは情報だけでなく、感情にも訴えるツールです。
依頼前に「伝えたい世界観」を一言で定義しておきましょう。
- 高級感(黒ベース・ゴールド系)
- 親しみやすさ(明るい色・丸ゴシック系フォント)
- 信頼感(ブルー系・余白多め)
失敗例
「おしゃれに」とだけ伝える→デザイナーの解釈と食い違いが発生
改善例
「スタバの広告のような雰囲気」と伝える→共通認識が持てる
デザイナーとのヒアリングを成功させるコツ
販促チラシ制作では、ヒアリング(打ち合わせ)の質が仕上がりを大きく左右します。
依頼者が「頭の中では分かっていること」を言語化できなければ、デザイナーはその意図をくみ取れません。
ここでは、ヒアリングを成功に導くための具体的なポイントを紹介します。
ゴールを最初に伝える
デザイナーにとって、ゴール(成果イメージ)が分からないまま作業に入ることほど危険なことはありません。
- ✗ NG:「売上を上げたい」→ 抽象的で、方向性が散漫になる
- ◯ OK:「新規オープン記念で、20代女性の来店を増やしたい」→ ターゲットや行動が具体的なので、写真や色使いに直結する
ワンポイント:
「このチラシを見た人に、どんな行動をしてほしいか」を一文で伝えるだけで、デザイナーは全体の構成を逆算できます。
優先順位を明示する(納期かデザイン性か)
チラシ制作では「理想と現実のせめぎ合い」が必ず発生します。
そこで大切なのが、何を優先するのかを最初に伝えることです。
- 「とにかく納期最優先」→ 最短で印刷に出せるよう、デザインはシンプルに
- 「多少時間をかけても、デザイン性を重視」→ 写真選び・配色などにこだわった仕上げが可能
- 「予算内で最大限の効果を」→ 紙質や印刷枚数の工夫でコスト最適化
✗ 失敗例:
「カッコよくしたいけど、明日までに」と後から言う → 修正が増え、完成度も下がる
制約条件を共有する
「予算」「紙質」「印刷枚数」といった制約条件は、デザインの選択肢を大きく左右します。
これを後から伝えると、せっかくのデザイン案が無駄になることも。
- 予算 → 片面印刷か両面か、カラーかモノクロか
- 紙質 → 高級感を出すならコート紙、手配りなら薄手のマット紙など
- 枚数 → 1,000枚と10,000枚では単価も戦略も変わる
実務ヒント:
印刷会社に見積もりを先に取っておくと、デザイナーが現実的なサイズ・仕様を提案しやすい。
成功するヒアリングのチェックリスト
言葉より画像の方が圧倒的に伝わりやすい
✅ ゴールを一文で言えるか?
「新商品を知ってほしい」ではなく「新商品Aを30代女性に知ってもらい、試食イベントに来てもらう」レベルまで具体化
✅ 誰に届けたいかを言語化できているか?
属性(年齢・性別)+心理(悩み・関心)まで掘り下げる
例:「忙しい共働き夫婦に“時短”を訴求」
✅ 使用シーンを想定しているか?
駅前で配布?DM同封?店頭置き? → レイアウト・サイズ・フォントに直結
✅ 必須要素を書き出したか?
店舗名/住所/電話番号/QRコード/キャンペーン期間
「載せ忘れたから追加」が一番コストと時間を浪費する
✅ イメージ参考を1つ以上用意したか?
「こういう雰囲気にしたい」という参考例(既存チラシ・Web広告・雑誌広告など)
よくある失敗例と改善ポイント
丸投げ依頼 → 想像と違う仕上がりに
失敗シーン
「チラシを作ってください。カッコよくお願いします!」
依頼時にこれだけしか伝えないケース、意外と多いんです。
その結果…
- デザイナーは自分の解釈で“カッコいい”を形にする
- 依頼者のイメージとズレる
- 「思ってたのと違う」と修正依頼が連発
悪影響
- 修正の往復で納期が遅れる
- デザイナーとの信頼関係が崩れる
- 最終的に妥協の産物になり、成果に直結しない
改善ポイント
最低限の“軸”を共有すること。
- 「目的」:来店促進? 認知拡大?
- 「ターゲット」:誰に届いてほしい?
- 「必須要素」:住所、電話番号、QRコードなど
参考:「おしゃれに」ではなく「スターバックスの新作告知のように」と言えば、イメージの共有度は一気に上がります。
情報過多 → 読者が疲れて読まない
失敗シーン
「せっかく作るなら全部載せたい」
→ メニュー、社長のメッセージ、沿革、スタッフ写真…結果、文字びっしり。
その結果…
- 見る人はどこから読めばいいか分からない
- パッと見で「面倒そう」と判断し、捨てられる
- 伝えたいコアメッセージが埋もれてしまう
悪影響
- チラシが「会社案内」に化けてしまう
- 読み手の記憶に何も残らない
- 印刷コストは上がるが、反応率は下がる
改善ポイント
勇気を持って「削る」。
- 「伝えたいことは3つ以内」に絞る
- そのほかはQRコードやWebページで補完
- 読者の視線が自然に流れるように配置
参考:
飲食店の新規オープンチラシで「全メニュー紹介」から「看板メニュー+限定特典」に変えたら、来店率が2倍になった事例もあります。
納期直前に方向転換 → 完成度が落ちる
失敗シーン
初回デザイン案はOKを出していたのに、印刷直前に「やっぱり全体の色を変えてほしい」「レイアウトをまるごと変えたい」と方向転換。
その結果…
- デザイナーが徹夜で修正 → クオリティ低下
- 印刷スケジュールに間に合わず、配布計画が崩れる
- 最悪、キャンペーン開始日にチラシが間に合わない
悪影響
- スタッフの疲弊、依頼者側のコスト増
- 「伝えたいこと」と「できること」が乖離する
- 最も重要な“成果”を逃す
改善ポイント
初期段階で方向性をしっかりすり合わせること。
- 初回打ち合わせで「デザインイメージ」「色味」「優先順位」を確認
- ラフ案(仮デザイン)の段階で大きな修正を済ませる
- 直前での変更は「文字修正」や「写真差し替え」程度に留める
参考:
大手流通企業の制作フローでは「ラフ案→方向性確定→清書」のステップを徹底し、直前の修正は“誤字脱字”レベルに抑えるルールがある。
実例で学ぶ「成功する依頼」
事例A:飲食店のオープン告知チラシ
Before:メニュー全掲載で文字びっしり
新規オープンする飲食店のオーナーは「せっかく作るなら全メニューを載せたい」と考えました。
チラシには料理名と価格がびっしり。さらに「店のこだわり」や「シェフの紹介」も細かい文字で書き込まれていました。
結果どうなったか?
- 見た人は「情報量が多すぎて、どこを読めばいいか分からない」
- 遠目では「文字の塊」にしか見えず、手に取っても読まずに捨てられる
- 「新規オープン」という一番伝えたい情報が埋もれてしまった
After:看板メニュー写真+「オープン記念特典」を前面に
デザイナーと相談し、「全メニュー紹介」から「看板メニュー1〜2品」に絞りました。
- 左上に大きな料理写真を配置(視線の入口にインパクトを与える)
- 中央に「オープン記念特典:ドリンク1杯無料」と太字で記載
- 下部には店舗情報とQRコードのみ
成果
- チラシを見た人が「おいしそう!」と一瞬で理解できるデザインに
- 「無料ドリンク」の行動喚起がわかりやすく、来店動機が明確に
- 来店率は従来の配布物と比べて 20%アップ
ポイント
「全部伝えるより“1つの魅力に絞る”方が行動につながる」
事例B:学習塾の春期講習チラシ
Before:説明文が長く、どこを読めばいいか分からない
学習塾では春期講習の告知チラシを作成。
担当者は「保護者に安心感を持ってもらうため、詳しく説明しよう」と考え、教育方針や授業内容を長文で記載しました。
結果どうなったか?
- 一目で「文字ばかり」に見え、保護者は読む気をなくす
- どの情報が重要なのか分からず、結局「捨てられるチラシ」に
- 問い合わせ件数は期待したほど伸びなかった
After:実績数値と「入会特典」を大きく表示
改善版では、「読む」より「見る」で理解できるデザインに転換。
- チラシ冒頭に「合格実績:志望校合格率90%」を大きく配置(信頼の数値化)
- 中央に「春期講習限定 入会金0円」の特典を目立たせる
- 詳細な教育方針や講座説明は小さめにまとめ、興味がある人はQRコードから詳細ページへ誘導
成果
- 保護者は「実績」と「特典」という判断材料を数秒で把握
- 「問い合わせしよう」と思わせるきっかけが明確に
- 結果、問い合わせ件数は 2倍以上に増加
ポイント
「長文説明より、数字+特典で“即効性”のある訴求を」
まとめ:成果を生む販促チラシ依頼のために
販促チラシをデザイナーに依頼するとき、闇雲に情報を渡すのではなく、最低限の5つの要素を整理することが成果を分けます。
目的
「売上を上げたい」では不十分。
「新規オープンの認知を広げたい」「リピーターを増やしたい」など、読者にどんな行動をしてほしいかを一文で言語化しましょう。
ターゲット
誰に届いてほしいかを明確にすることが、デザインの方向性を決めます。
年齢・性別・ライフスタイル・心理状態まで具体的に描くと、写真・コピー・配色の選定がブレません。
配布シーン
駅前で配布するのか、DMで送るのか、店頭に置くのか。
渡す場所や状況によって、文字サイズ・情報量・紙質は大きく変わるため、事前に想定して共有することが重要です。
必須要素
住所・電話番号・QRコード・キャンペーン期間など、抜けたらチラシとして成立しない情報は必ずリスト化して渡しましょう。
「後から追加」になると、デザインの再構成が必要になり、コストも納期も圧迫されます。
トーン&イメージ
同じ内容でも、デザインの雰囲気によって受け手の印象は大きく変わります。
「高級感を出したい」「親しみやすさを重視したい」など、方向性を一言で伝えるだけで、デザイナーとのイメージのすり合わせが格段にラクになります。
重要なのは、完璧に決めてから依頼する必要はないということ。
デザイナーは「完成形を一緒に探すパートナー」です。
未完成の状態であっても、軸さえ共有できていれば、デザイナーはその情報をもとに具体化・提案してくれます。
ただし、丸投げはNG。
「任せる=考えなくていい」ではなく、「任せる=一緒に作る」という意識を持つことが、成果に直結する依頼の姿勢です。
👉 つまり、チラシ制作で成功したいなら、
- 5つの要素を整理する
- デザイナーと共通言語を持つ
- 丸投げではなくパートナーシップを築く
これだけを実践するだけで、あなたの販促チラシは“ただの紙”から“人を動かすツール”へと変わります。